最近、「フィギュアスケートがつまらなくなった」「昔のほうが見応えがあった」という声をSNSでよく見かけます。
かつては一つひとつの演技に息をのむような感動があり、選手たちのドラマが世界中を熱狂させていました。
しかし今、「ルール改正で分かりにくくなった」「ロシア勢がいないと華やかさが足りない」など、さまざまな理由から“つまらなくなった”と感じる人が増えています。
この記事では、そうした声の背景や“レベル低下”の真相を、ファンの意見と専門的な視点の両面から分かりやすく解説します。
華やかな氷上の裏で何が起きているのか──今だからこそ知っておきたい内容です。
フィギュアスケートが「つまらない」と言われるようになった背景

かつては冬季五輪の花形競技として絶大な人気を誇ったフィギュアスケート。
ですが近年、「昔ほどワクワクしない」「演技が淡々としている」といった声が増えています。
その背景には、ルール改定や採点方式の複雑化、ロシア勢の不在、そしてテレビ放送の減少など、さまざまな要素が重なっているようです。
SNS上でも「昔の方がストーリー性があった」「最近は技術だけって感じ」という投稿が多く見られます。
技術偏重の採点傾向
特に多く見られる意見が、「ジャンプばかりで芸術性が薄れた」というもの。
現在の採点システム(ISUジャッジングシステム)は技術点(TES)と演技構成点(PCS)に分かれていますが、実際は技術点の影響が非常に大きいのが現実です。
そのため、「音楽と一体となった美しい演技」よりも、「高難度ジャンプを確実に決めること」が重視される傾向に。
SNSでは「技術はすごいけど心が動かない」「ジャンプ大会みたい」といった声も目立ちます。
採点基準の複雑化と不透明さ
現在の採点方式では、回転不足やエッジエラーなど細かな判定が得点に大きく影響します。
見た目には成功しているように見える演技でも、採点では減点対象になることがあり、「なんでこの人の点数が低いの?」と感じる視聴者も少なくありません。
こうした“わかりにくさ”が、競技本来の魅力を損なっているという指摘もあります。
ロシア勢の不在によるレベル・話題性の低下
ロシア選手が国際大会から除外されたことで、特に女子シングルの勢力図が一変しました。
かつてはワリエワやトルソワのように、4回転ジャンプを次々と成功させる選手が観客を沸かせていました。
SNSでは「ロシア勢の高難度ジャンプは異次元だった」「またあの演技が見たい」との声も多く、彼女たちの存在感の大きさを改めて感じさせます。
一方で、ロシア不在により“ジャンプ合戦”が落ち着いたことで、技術的な迫力や話題性が減ったと感じる人もいるようです。
フィギュアスケートでロシアが出ていない理由についてはこちらにまとめてありますので、ぜひこちらもご覧ください。
放送・演出の減少による“熱狂の薄れ”
以前はゴールデンタイムで放送されていた大会も、現在は深夜枠や配信中心へ。
中継番組での密着企画や感動ドキュメントも減り、「ストーリーとして楽しむ要素がなくなった」という声もあります。
視聴環境の変化によって“競技を見守る時間”そのものが減り、かつてのような国民的熱狂が生まれにくくなっているのかもしれません。
若手選手の個性・スター性の不足
浅田真央さんや羽生結弦さんのような“誰もが知るスター”がいた時代と比べると、新世代は実力は十分でも、まだ個性や物語性で強く印象づける選手は少ない印象です。
ただ、これは「時代の変化」でもあります。
今はSNSや動画配信を通して、選手が自ら発信する時代。スターの形が変わりつつあると言えるでしょう。
レベルが落ちたって本当?技術面・戦略面から検証

「レベルが落ちた」という意見は確かに多いですが、実際のところは少し違います。
女子では4回転ジャンプを跳ぶ選手が減り、派手さが減ったのは事実。
SNSでも「女子の4回転が見られなくなって寂しい」「昔の方が迫力があった」という投稿が目立ちます。
しかし今は、ジャンプの正確さやスケーティング全体の完成度が格段に上がっており、“質”の時代とも言えます。
技の難易度だけでなく、演技構成や表現力の完成度で勝負する選手が増えているのです。
戦略面:安定志向の台頭
採点システムの改定で、高難度ジャンプのリスクとリターンのバランスが変化。
失敗による減点が大きいため、選手は確実に加点を重ねる“安定構成”を選ぶ傾向にあります。
こうした“戦略的保守化”が、「昔より攻めなくなった」と見える要因になっています。
ただし、これは戦略が進化した証でもあり、「勝つためにどこでリスクを取るか」を考える戦術性の高い時代とも言えます。
採点制度や大会の変化がもたらす”印象の違い”

フィギュアスケートはルールが少し変わるだけで“見え方”が大きく変わる競技です。
たとえば──
- 採点の透明化で公平性は増したが、システムが複雑に感じる
- 技術だけでなく表現力も重視されるようになった
- 選手がリスクより得点効率を重視する戦略へシフト
- 観客も「感動より分析」で観る傾向が強まっている
こうした変化が、「昔のような熱狂がない」と言われる一方で、“技術芸術競技”としての進化を支えているのです。
今だからこそ注目したい!新世代スケーターと競技の進化
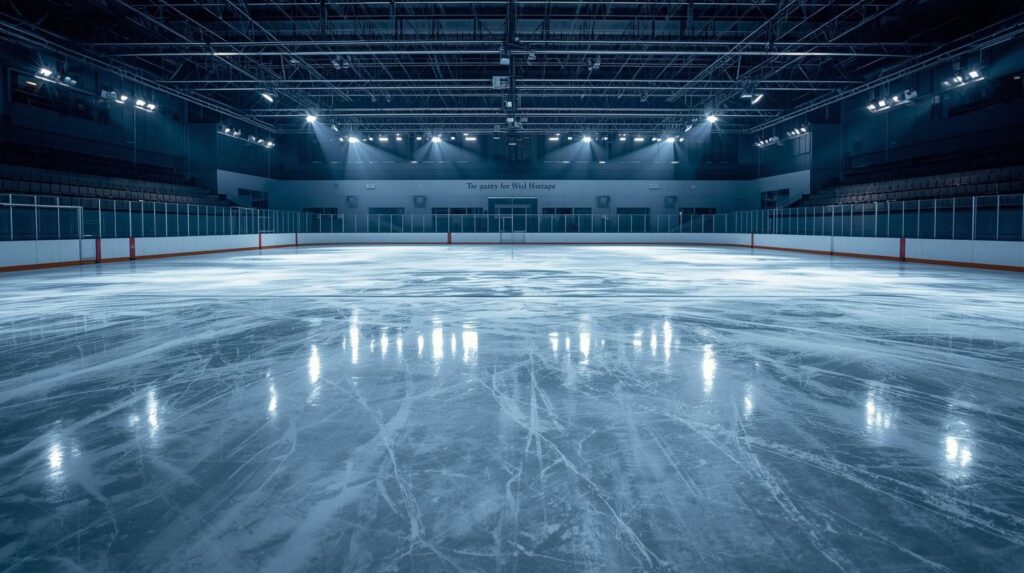
近年のフィギュア界では、新しい才能が次々と登場しています。
【男子シングル】
・鍵山優真:北京五輪銀メダリスト。ジャンプの安定感と繊細な表現力が武器。
・三浦佳生:多彩な4回転ジャンプを操る実力派。演技面でも評価上昇中。
【女子シングル】
・島田麻央:4回転やトリプルアクセルに挑戦する若き実力者。
・千葉百音:世界選手権銅メダリスト。完成度とスケーティングの美しさが魅力。
・坂本花織:世界選手権3連覇。安定感と表現力で女子の頂点に立つ。
また、ルールや年齢制限の見直し、安全性向上など、競技そのものも進化を続けています。
派手な“ジャンプ合戦”の時代から、“完成度と個性で魅せる時代”へ──。新しいフィギュアスケートの幕が上がっています。
まとめ
フィギュアスケートが「つまらなくなった」と言われるのは、競技の質が落ちたのではなく、“見え方”が変わったから。
挑戦よりも完成度を重視する時代になり、派手さは減っても、技術・芸術・戦略が融合した“成熟の競技”に進化しています。
そして今、若い選手たちがそのルールの中で「自分らしさ」を表現しようとしています。
静かな氷上に込められた新しいドラマ──それこそが、次のフィギュアスケートを再び熱くする鍵になるでしょう。

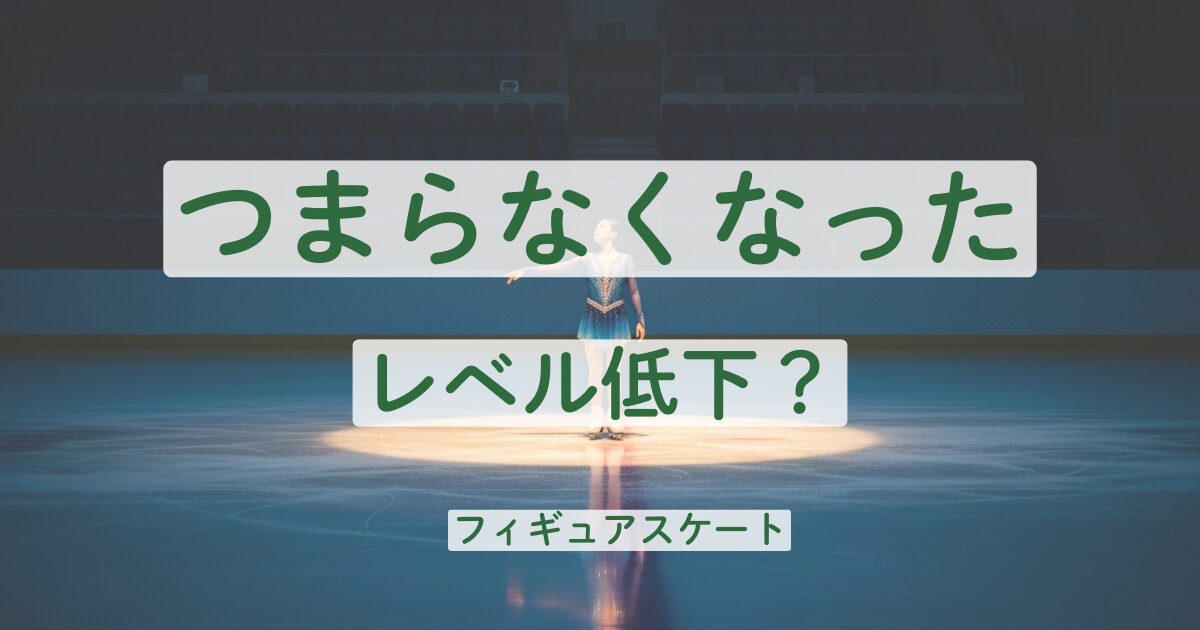
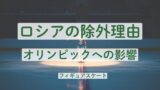


コメント